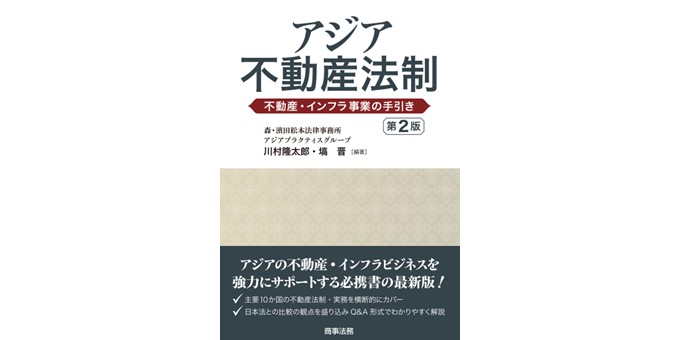中国の「標準必須特許独占禁止ガイドライン」の公布・施行
Ⅰ. はじめに
中国国家市場監督管理総局は、2024年11月4日に「標準必須特許独占禁止ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)を公布・施行しました。
本ガイドラインは、標準必須特許(標準の実施に不可欠な特許のこと)の濫用により競争を排除し、制限する行為を防ぐために、事前及び実施中の監督管理措置、標準必須特許の権利者を対象とする良好な慣行、関連する独占合意、市場支配的地位の認定に関する考慮要素等を規定しており、6章、22個の条文から構成されています。
Ⅱ. 本ガイドラインの概要
1.総則(定義・一般原則・事前及び実施中の監督管理措置)
本ガイドラインのうち1条から5条は、第1章に含まれており、3条で、標準必須特許の濫用による競争
の排除または制限の判断は、独占禁止法に基づいて行うとしたうえで、①知的財産権の濫用による競争の排除または制限と同様の分析思考を採用すること、②知的財産権の保護と市場における公正な競争の維持のバランスをとること、③標準必須特許権者と標準実施者の利益のバランスをとること、④標準の策定と実施の過程において、標準必須特許に関連する情報の開示、実施許諾の合意、実施許諾にかかる協議を十分に考慮することという基本原則を掲げています。
続く4条では、関連市場の判断方法について記載しています。具体的には、標準必須特許が関係する関連商品市場は、主に技術市場及び標準の実施に関わる製品・サービス市場であり、このうち、技術市場は、需要代替分析に関して、異なる標準間、異なる標準必須特許間、標準必須特許と非標準必須特許間、標準必須特許と非特許技術間に緊密な代替関係があるかどうかという観点から分析することができ、必要に応じて、供給代替分析を同時に行うことができるとしています。
事前及び実施中の監督管理措置についての規定である5条では、標準の制定及び実施、パテントプールの管理又は運営、標準必須特許の実施許諾の過程において、標準設定機関、パテントプールの管理・運営機関、標準必須特許の保有者、標準の実施者等の事業者は、競争の排除又は制限のリスクを発見した際に当局に自主報告できること、競争排除・制限のおそれがある場合、または独占行為を行う疑いがある場合、当局は、注意喚起、事情聴取・是正などの手段により、事前・事後の監督を強化し、標準設定機関、パテントプールの管理・運営機関、標準必須特許の保有者、標準の実施者等の事業者に対して、改善措置を打ち出し、関連問題の予防・是正を行うよう求めることができることを規定しています(5条)。
2.標準必須特許の権利者を対象とする良好な慣行
第2章に含まれる6条から8条では、標準必須特許の権利者を対象とする良好な慣行が挙げられています。具体的には、①事業者は、自ら保有している必須特許を適時に完全に開示し、同時に対応する裏付け資料を提供すること(6条)、②標準の作成・改訂に参加する特許権者等は、特許実施許諾に関する宣言を明確に行い、公平、合理、無差別の原則に基づいて、他の事業者が標準の実施において特許を使用することを無償または有償で許諾することに同意すること(7条)、③標準必須特許の権利者と標準実施者は、標準必須特許の実施許諾の料率、数量、期限、使用範囲、地理的範囲などの実施許諾条件について、公正、合理的、無差別的な実施許諾条件に達するよう、両者間で誠実に交渉すること(8条)が挙げられています。そのうえで、これらの良好な慣行に従わないことは、必ずしも独占禁止法違反につながるわけではないものの、競争の排除や制限のリスクを高める可能性があるとしています。
3.標準必須特許に関わる独占合意
9条から11条は第3章を構成しており、標準必須特許に関わる独占合意の判断方法が規定されています。標準必須特許に関わる独占合意の判断に際しては、独占禁止法、独占合意禁止規定、競争行為を排除または制限するための知的財産権の濫用禁止規定およびその他の関連規定を適用するとしたうえで、標準制定及び実施過程における独占合意(9条)、標準必須特許に係るパテントプールに関連する独占合意(10条)、標準必須特許に関するその他の独占合意(11条)という場合に分けて、独占合意の考慮要素を規定しています。例えば、標準制定及び実施過程における独占合意に関しては、具体的な分析において考慮できる状況について、①他の特定の事業者が規格設定に参加することを排除する正当な理由がないかどうか、②他の特定の事業者を関連プログラムから排除する正当な理由がないかどうか、③他の競合する規格を実施しないことに合意する正当な理由がないかどうか、④特定の規格実施事業者が、当該規格に基づく試験の実施、認証の取得等の規格実施活動をすることを制限する正当な理由がないか等を挙げています。また、標準必須特許に係るパテントプールに関連する独占合意の具体的な分析において考慮できる状況については、①標準必須特許権者がパテントプールを利用して、価格、生産量、市場区分などの競争に関するセンシティブ情報を交換しているかどうか、②パテントプールの管理または運営の対象に、パテントプール内の競合特許が含まれるかどうか、③パテントプールの管理または運営において、標準必須特許の所有者が単独で当該特許の実施許諾を行うことを共同で制限しているかどうか、④パテントプールの管理又は運営において、標準必須特許権者が独占合意を締結するよう組織されているか、又は標準必須特許権者が独占合意を締結することを実質的に援助しているか等を挙げています。
4.標準必須特許に関わる市場支配的地位の濫用
第4章を構成する12条から18条は、標準必須特許に関わる市場支配的地位の濫用について規定しています。12条では、標準必須特許の所有者が関連市場において支配的地位を有するか否かを判断するための考慮要素として、①関連市場における標準必須特許権者の市場占有率、関連市場における競争状況(通常、代替規格がない場合、それを否定する十分な証拠がない限り、標準必須特許のライセンス市場において、標準必須特許の権利者が全市場を占めていると推定される)、②標準必須特許権者が関連市場を支配する能力(これには主に、標準必須特許権者が実施料率、実施方法などの実施条件を決定する能力、他の事業者が関連市場に参入することを妨害し、影響を与える能力、標準実施者が標準必須特許権者を制約する客観的条件と実際の能力などが含まれる)、③標準必須特許に対する川下市場の依存度(これには主に、対応する標準の進歩、代替可能性、スイッチングコスト等が含まれる)、④他の特許権者がライセンス市場に参入する難易度(これには主に、標準必須特許技術が代替される可能性などが含まれる)、⑤標準必須特許の所有者の財務状況や技術状況など、市場支配力の判断に関連するその他の要素を挙げています。そのうえで、市場支配的地位の認定に関する考慮要素について、①不公平な高価格により標準必須特許を許諾する場合、②標準必須特許の許諾を拒絶する場合、③標準必須特許に係る抱き合わせ販売の場合と、場合に分けて考慮要素が規定されています(13~15条)。
5. その他
本ガイドラインの19条は、標準必須特許に関わる事業者間の取引が、事業者集中を構成する可能性があり、標準必須特許に関わる取引が事業者集中に該当するか否かの判断は、独占禁止法、関連するガイドライン及び関連する独占禁止規定に基づいて分析するものとするが、①標準必須特許がカバーする製品またはサービスが独立した事業を構成するか、または独立した計算可能な売上高を生み出すかどうか、②標準必須特許の実施許諾の方法と期間という要素も考慮することができるとしています。
そして、標準必須特許を含む取引が事業者の集中に該当し、事業者集中の届出要件を充足する場合、事業者集中にかかる届出が必要であり、届出及び当局のクリアランスがなければ集中を実施してはならない旨を規定しています。
「事業者集中に対する独占禁止法簡易審査届出書」と「事業者集中に対する独占禁止法簡易審査公示表」の改訂
中国国家市場監督管理総局は、2024年9月14日に、「事業者集中に対する独占禁止法簡易審査届出書」と「事業者集中に対する独占禁止法簡易審査公示表」の改訂版(以下「簡易届出書等」と総称します。)1を公表し、2024年10月12日から施行されています。
簡易届出書等では、届出書に記載すべき項目内容が削減されるなど大幅な改訂がなされていますが、以下では、実務への影響が比較的に大きいと考えられる届出資料に関する主要な改訂内容を簡潔にご紹介します。
(1) 届出資料の削減
以前は、届出の際、届出書のうち機密情報を含むバージョン、届出書のうち機密情報を含まないバージョン、公示表という3つの資料を提出する必要があったところ、届出書のうち機密情報を含まないバージョンは今後提出不要となりました。
(2) 競争影響評価の提出等に関する緩和
改訂された簡易届出書等においては、以下のア)、イ)、ウ)の類型に応じて、従前は届出資料として提出が必要であった競争影響評価に関して、提出義務や提出時期、提出方法等が緩和されています。
ア)市場シェアデータ・その他の競争分析の提出が不要な場合
・ 集中に参加する事業者が中国国外に合弁企業を設立し、合弁企業が中国国内において経済活動に従事しないとき
・ 集中に参加する事業者が国外企業の持分又は資産を買収し、当該国外企業が中国国内において経済活動に従事しないとき
イ)当初の届出資料において競争分析の提出が不要な場合(ただし、審査の際に当局は、必要な場合、競争分析の提供を要求することができる)
・関連市場における当事者の合算市場シェアが15%を超えない水平型の事業者集中
・関連市場における各当事者のシェアがいずれも25%を超えない垂直型・複合型の事業者集中
・ 2つ以上の事業者が共同支配する合弁企業が、集中を通じてそのうちの1つ又は1つ以上の事業者によって支配されるとき
ウ)一定の状況において競合他社の市場シェアデータの提供が免除される場合
・関連市場における当事者の合算市場シェアが5%を超えない水平型の事業者集中
・関連市場における各当事者のシェアが5%を超えない非水平型の事業者集中
上記の事業者集中において、当事会社が業界が認める第三者が公表する市場シェアデータを入手することが困難な場合、当事会社の市場シェアデータおよび市場全体の規模データのみを提供することが認められます。ただし、当局は必要と認めた際に、当事者に競争者の市場データを提供するよう要求することができるとしています。