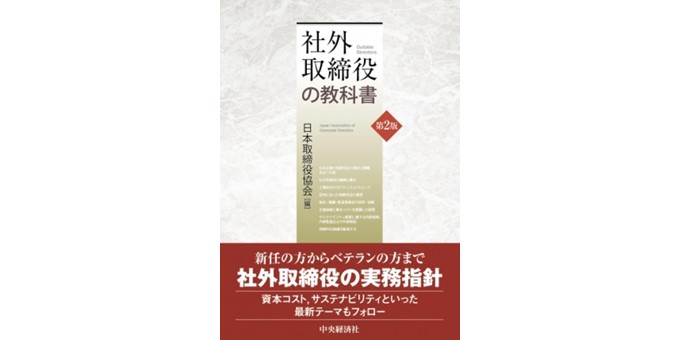Ⅰ. はじめに
公益通報者保護法を改正する法律が、2025年6月4日に第217回通常国会において成立し、同月11日に公布されました(以下、改正後の公益通報者保護法を「改正法」といいます。)。
公益通報者保護法(以下、「法」といいます。)は、2004年に制定され、2020年に初めての改正(2022年に施行)が行われました。その際、施行後3年を目途に見直すことが附則において定められていました。かかる附則を踏まえ、消費者庁は、公益通報者保護制度検討会(2024年5月7日から同年12月まで)を開催し、同年12月27日に「公益通報者保護制度検討会報告書-制度の実効性向上による国民生活の安心と安全の確保に向けて-」を取りまとめ、同報告書の内容を踏まえた改正法案が立案され、今般の改正に至りました。
改正法は、主に公益通報者保護制度の実効性を向上させ、公益通報者の保護をより一層強固にする観点からの改正となっています。各企業における公益通報(内部通報)への対応にも影響する内容となっており、各企業においては改正法の内容を踏まえた社内の規程類の見直しや内部通報への対応のあり方の確認をする必要がありますので、本号にて解説します。
Ⅱ. 改正法の概要
今般の改正法の内容は、以下の4つの観点に大別できます。
| ① 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上 ② 公益通報者の範囲拡大 ③ 公益通報を阻害する要因への対処 ④ 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化 |
それぞれの改正項目の概要は下表のとおりです。
【改正法の概要】
| 改正の趣旨 | 具体的な改正内容 | 改正法の条文 |
|---|---|---|
| 1. 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上 | (1) 従事者指定義務の違反に対する担保措置の拡充 (命令権や立入検査、罰則等の新設) | 15条の2、16条、21条、23条 |
| (2) 内部通報制度の周知義務の明示 | 11条2項 | |
| 2. 公益通報者の範囲拡大 | (1) 公益通報者の範囲にフリーランスを追加 | 2条、5条 |
| 3. 公益通報を阻害する要因への対処 | (1) 公益通報を妨げる行為の禁止 | 11条の2 |
| (2) 公益通報者を特定することを目的とする行為の禁止 | 11条の3 | |
| 4. 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化 | (1) 公益通報を理由とした解雇・懲戒の推定 (立証責任の転換) | 3条3項 |
| (2) 公益通報を理由とした解雇・懲戒に対する刑事罰 | 3条、21条、23条 |
1. 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
(1)従事者指定義務の違反に対する担保措置の拡充(改正法15条の2、16条、21条、23条関係)
①現行法の規定
現行法は、事業者に従事者1を定める義務を課しており(法11条1項)、当該義務の履行を担保すべく、消費者庁2に、報告徴収、助言指導、勧告、勧告に従わない場合の公表の権限を付与しています(法15条、16条)。
また、現行法では、従事者を指定した場合、従事者(であった者)は刑事罰付きの守秘義務を負うものの(法12条、21条)、事業者は、従事者指定義務に違反した場合であっても刑事罰の対象にはなりません。そのため、事業者に対する刑事罰が規定されていないことが従事者指定義務の履行に関するディスインセンティブとなり、結果として、事業者が従業員を守るという観点からあえて従事者指定を行わないケースがあるなど、当該義務の履行が徹底されないという一面がありました。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、このようなディスインセンティブを解消し、また、従事者指定義務違反に対する行政措置権限を強化する観点から、消費者庁に、事業者3が従事者指定義務(改正法11条1項)に違反し、勧告に従わなかった場合における命令権を付与し(改正法15条の2第2項)、命令に従わない場合には事業者に対して刑事罰(30万円以下の罰金、両罰規定4)を科すこととしました(改正法21条2項1号、23条1項2号)5。
前記に関連して、改正法は、同じく消費者庁の行政措置権限を強化する観点から、現行法下では定められていなかった事業者への立入検査に関する権限を付与するとともに(改正法16条1項)、立入検査を拒否した事業者に刑事罰(30万円以下の罰金、両罰規定)を科すこととしました(改正法21条2項2号、23条1項2号)。
このように、改正法の施行後は、命令権や立入検査など、消費者庁の従事者指定義務の履行への強制力が高まることから、従事者指定が適切に実施されているかを改めて見直す必要があります。また、仮に消費者庁から調査が行われたとしても従事者指定が適切に実施されていることを示すことができるよう、従事者指定に関する書類などの義務履行に関する証跡を適切に作成・保管しておくことが重要になると考えられます。
(2)内部通報制度の周知義務の明示(改正法11条2項関係)
①現行法の規定
現行法は、内部公益通報対応体制の整備等の義務について、「適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置」をとることのみを定めています(法11条2項)。その具体的な措置の内容については、法定指針6が必要な事項を定めており、「労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置」として、従業員に対する周知の実施などを規定しています(指針第4・3(1)イ)。
しかし、2023年度における消費者庁の実態調査などにおいて、内部通報制度の周知が十分ではないこと、一方でその周知が内部通報制度の利用を促進することなどが指摘されています。実際に、当職らが日々取り扱っている事案においても、内部通報制度の周知が十分ではないことが不正・不祥事の発生の一因となっている場合が多々あります。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、内部通報制度の周知を徹底し、その実効性を向上させる観点から、内部公益通報対応体制の整備等の義務の例示として「労働者等に対するその周知」を法律上明示しました(改正法11条2項)。
法定指針から、現行法下でも内部通報制度の周知を実施しない事業者は内部公益通報対応体制の整備等の義務違反となりますが、今後は、改正法があえてその周知義務を例示した趣旨を踏まえて、内部通報制度についてより一層の周知徹底を図ることが求められます。具体的には、従業員が目にしやすい社内イントラネットのトップページに内部通報窓口の連絡先を掲載することや、内部通報窓口の連絡先を記載した携帯用カードを配布すること、定期的な内部通報に関するセミナーや研修を実施すること等の手法により、従業員に対して内部通報制度の周知徹底を図ることが考えられます。
2. 公益通報者の範囲拡大(改正法2条1項3号、5条関係)
①現行法の規定
現行法は、公益通報の主体を労働者や派遣労働者のほか、退職後1年以内の者、役員、一定の取引先労働者等と定めており(法2条1項各号)、昨今増加しているフリーランスは公益通報の主体に含まれていません。
他方で、フリーランスは、既に通報主体とされている労働者等と同様に取引先の不正を知り得る上に、労働者に準ずる弱い立場にあって不利益な取扱いを受ける懸念があると考えられています。そのため、フリーランスについても現行法の公益通報の主体と同様に保護されるべきとの意見があったところです。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、公益通報の主体にフリーランス(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条2項に規定する特定受託業務従事者をいい、通報日前1年以内にフリーランスとして業務を受託していた者を含みます。)を追加しました(改正法2条1項3号)。
したがって、内部通報制度の利用者としてフリーランスを含めていない事業者においては、社内規程を改訂する必要があります。具体的には、フリーランスについても公益通報の主体として規定し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することなどを規定する必要があり、この規定に従って運用されるように役職員等に対して周知・教育することも重要です。
3. 公益通報を阻害する要因への対処
(1)公益通報を妨げる行為の禁止(改正法11条の2関係)
①現行法の規定
現行法は、公益通報を行おうとする者が安心して通報できるよう、公益通報を理由とした解雇の無効や不利益な取扱いの禁止等を規定することで公益通報者を保護しています。他方で、公益通報を行うこと自体に対する妨害行為に対処する明文の規定はありません。
現行法においても、仮に事業者と労働者が「どのような状況であっても公益通報はしません」といった合意をした場合、当該合意は民法の一般原則に照らして公序良俗に反して無効になると考えられます。しかし、公序良俗に反するか否かは労働者にとって明確ではなく、最終的には裁判所の判断に依るため、公益通報を行おうとしている者が委縮し、公益通報を妨げてしまう可能性がありました。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をするよう求めることや、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすると告げることなどの公益通報を妨害する行為を禁止しました(改正法11条の2第1項)。かかる規定により、例えば、前記のような合意はもちろん、「公益通報をした場合には地方に異動させるから覚悟するように」と告げることや、公益通報を躊躇するよう第三者を利用して圧力をかけることも違法となると考えられます。また、改正法は、公益通報を妨げることになる行為が法律行為(例えば、前記のような公益通報をしない旨の合意)である場合はこれを無効としました(改正法11条の2第2項)。ただし、このような公益通報を妨げる行為については、刑事罰の対象とはされていません。
なお、公益通報をしない旨の合意については、事業者と労働者との間の守秘義務との関係でも問題となり得る場面が想定されるため、「正当な理由」(改正法11条の2第1項)の具体例や解釈は実務上重要となります。消費者庁は、「正当な理由」について、「例外的かつ限定的な場合にとどめるべき」との一般論のもと、例えば「労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく単なる思い込みで報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めること」は該当し得るとしています7。
(2)公益通報者の特定を目的とする行為の禁止(改正法11条の3関係)
①現行法の規定
現行法は、内部公益通報対応体制の整備等の義務について「適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置」をとることのみを定め(法11条2項)、その具体的な内容は法定指針に定めています。法定指針は、事業者に対し、公益通報者の探索行為を防ぐための措置を講じ、探索行為があった場合は懲戒処分等の適切な措置をとることを規定しています(指針の第4・2(2)ロ、ハ)。
他方で、公益通報者を探索する行為が公益通報者に対して不安を与え、結果として内部通報制度が活用されなくなってしまうことについて、事業者の理解が十分ではないということが指摘されてきました。また、法定指針で規定されているのはあくまで探索行為を防ぐための措置であって、公益通報者を探索する行為を直接禁じているものではないこともあり、公益通報者は自分が探索されるかもしれないとの懸念を払拭できず、通報を阻害する要因の一つとなっていました。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、正当な理由なく、公益通報者である旨を明らかにするよう要求する行為など、公益通報者の特定を目的とする行為を禁止しました(改正法11条の3)。この「正当な理由」(改正法11条の3)については、消費者庁からは「例外的かつ限定的な場合にとどめるべき」との一般論が示されているところ、具体的には、通報者の情報を把握しなければ必要な調査が実施できない場合に、従事者が公益通報者に対して詳細な情報を問う行為等が想定されます。
公益通報者の探索行為を禁じることが明示されたことにより、公益通報者の心理的安全性が確保され、内部通報制度の利用促進につながることが期待されます。
実務的な観点としては、現行法下でも事業者は公益通報者の探索防止措置を講じなければならないので、事業者にとって新たな義務が課されたわけではありません。しかし、改正法施行後は、公益通報者の探索行為が明確に法令違反となることを踏まえ、事業者においては、公益通報者の探索行為が行われないよう、役職員に対し一層の徹底を図るとともに、違反者に対しては厳正な処分をすることが考えられます。
4. 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化
(1)公益通報を理由とした解雇・懲戒の推定(立証責任の転換)(改正法3条3項関係)
①現行法の規定
現行法では、不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任は公益通報者である労働者が負うことになります。しかし、事業者と労働者の情報の偏在等から、一般的に、労働者がこの点を主張・立証することは困難です。
この点については、前回の改正(2020年)時から検討課題とされていましたが、人事権の行使は使用者側に広い裁量が認められることなどから、改正が見送られた経緯があります。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、公益通報をした日(行政機関やマスコミ等の外部への公益通報の場合は事業者が当該公益通報を知った日)から1年以内の解雇・懲戒については、公益通報を理由としてされたものと推定することとし、立証責任を事業者に転換しました(改正法3条3項)。
実務上の観点からは、立証責任が転換されることを踏まえ、事業者は、解雇や懲戒処分を検討する過程において、その解雇・懲戒処分が公益通報以外の理由により行われていることを立証できるだけの資料や記録を作成することが必要となると考えられます。
(2)公益通報を理由とした解雇・懲戒に対する刑事罰(改正法3条、21条、23条関係)
①現行法の規定
現行法は、公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止していますが(法5条)、これに違反した場合の刑事罰を定めていません。しかし、不利益な取扱いについては、民事裁判を通じて事後的な救済を図る負担は大きく、労働者が通報を躊躇する大きな要因となっていると指摘されてきました8。
②改正法の概要と実務上のポイント
改正法は、公益通報を理由とした解雇・懲戒をした個人に対して刑事罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)を科すとともに、事業者も刑事罰(法人の場合3,000万円以下の罰金)の対象にすることとしました(改正法21条1項、23条1項2号)。ただし、刑事罰の対象となる行為の明確性の観点から、解雇・懲戒以外の不利益な取扱い(不利益な配置転換や嫌がらせ等)は刑事罰の対象とはされていません。
5. 施行時期・経過措置等
改正法は、公布の日から1年6月以内に施行されます(改正法の附則1条)。そして、改正法の施行日までには法定指針や指針の解説の改訂も見込まれています。そのため、各企業においても、改正法や改訂後の法定指針等を踏まえた社内規程の改訂等の対応が必要になると考えられます。
また、改正法は、原則として施行前に行われた公益通報にも適用されますが(改正法の附則2条)、いくつかの特則が定められている点には留意が必要です。例えば、改正法の施行前に懲戒処分として減給がされた場合については立証責任を転換する規定(改正法3条3項)が適用されませんが(附則3条2項)、解雇については改正法の施行前に行われたものでも立証責任を転換する規定が適用されます(附則3条3項)。また、改正法の施行前に公益通報をしない旨の合意をした場合は、当該合意を無効とする規定(改正法11の2第2項)は適用されません(附則5条)9。
Ⅲ. おわりに
以上のとおり、改正法は、公益通報者保護制度の実効性を向上させるために、既に法定指針において規定されていた周知義務や公益通報者の探索禁止等を法律に規定し、また、消費者庁の行政措置権限を強化していますので、今後、消費者庁による執行がより積極的に行われる可能性があります。
事業者の皆様におかれましては、改正法を踏まえた社内の規程類の見直しに加えて、今一度、法及び社内の規程類に従った運用がなされているかを確認することが肝要です。また、今後、法定指針や法定指針の解説の改訂等も想定されるため、これらの動向にも引き続き注視する必要があります。
- 法3条1号及び6条1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者をいいます(法11条1項)。
- 法による権限は、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任されています(法19条)。本稿では分かりやすさの観点から、法の執行主体について単に消費者庁と記載します。
- 義務対象事業者(常時使用する労働者の数が300人超の事業者)に限られます。
- 行為者本人だけでなく、その行為者と一定の関係にある法人等の事業者をも処罰する旨の規定をいいます。
- 従事者指定義務とは異なり、内部公益通報対応体制の整備等の義務(改正法11条2項)の違反については、現行法から変更なく、消費者庁の命令権限や刑事罰はありません。後述の立入検査についても同様です。
- 法11条1項及び2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針をいいます。
- 第217回国会参議院消費者問題に関する特別委員会2025年5月16日伊東大臣答弁等。なお、この場合は3号通報の保護要件を満たさないと考えられます。
- 消費者庁が公表した「内部通報制度に関する意識調査-就労者一万人アンケート調査の結果-」(2024年2月29日)によれば、勤務先で重大な法令違反行為を知った場合、「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答し、かつ、「最初に通報する先」として勤務先を選択した者の62.6%が匿名通報を希望しています。この理由について、その57.4%が「実名で相談・通報すると、勤め先から「問題のある人物」と思われ、人事異動・評価・待遇面などで不利益な取扱いを受けるおそれがあるから」と回答しています。
- もっとも、前記のとおり、民法の一般原則に照らして公序良俗に反して無効になる可能性はあります。